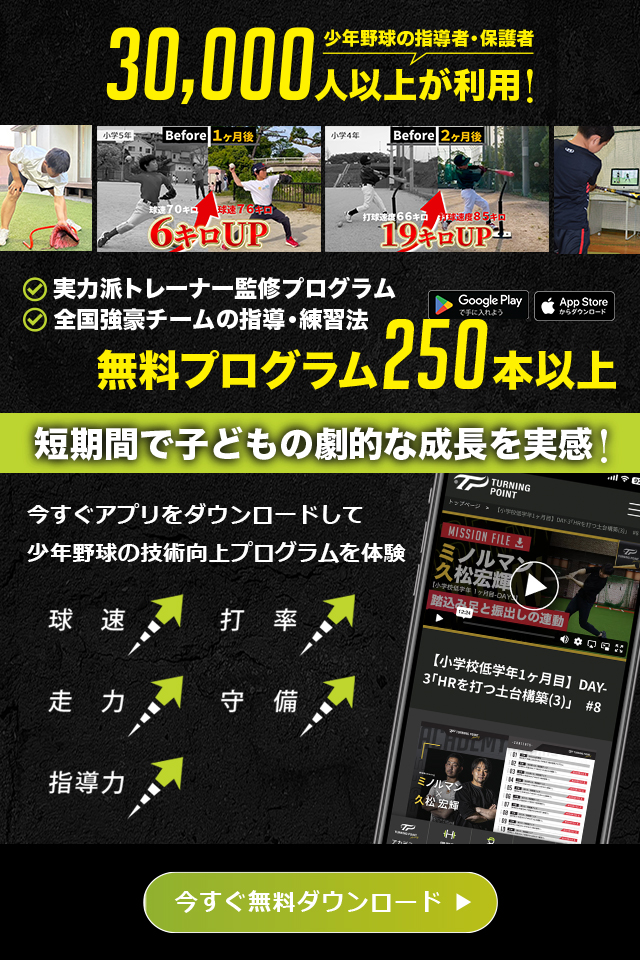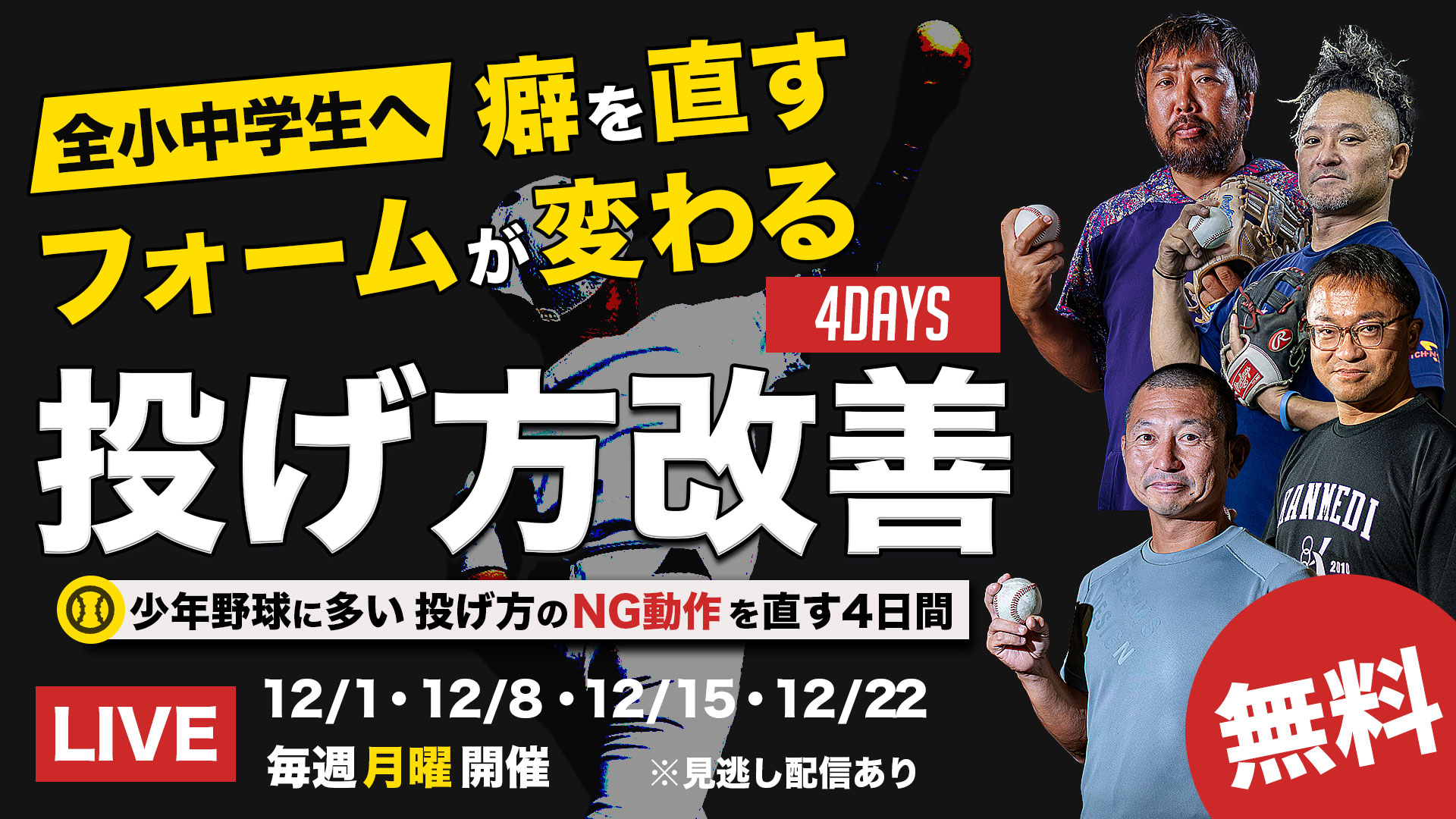【少年野球ダイジェスト】野球と勉強との両立は精神論でなく「技術」子どもの自主性を引き出すヒント(’25 9/28)
本日の注目テーマは「野球と勉強の両立」という多くの選手・保護者の課題を解決する具体的な技術と、試合で活きる「守備」と「走塁」の基本動作を習得する練習法についてお届けします。
・野球と勉強の両立は「技術」。元東大監督らが実践するやる気を引き出すヒント
(参考:First-Pitch - 学習)
野球と勉強の両立の鍵はどの家庭でも直面する課題です。実際に"文武両道"を実践した野球人の中に、子どもを導くヒントが隠されています。元東大野球部監督の浜田一志さんは、成長が実感できる「指標の設定」が重要だと語り、小学生には「九九素振り」を推奨。「知識の蓄積」を指標にすることでモチベーション維持に繋がるといいます。慶応、早実でそれぞれ甲子園出場経験を持つ鈴木裕司さん、健介さん兄弟は、試験1週間前は勉強に集中する「メリハリ」を実践し、具体的な目標を壁に貼って意識していました。また、NPB入りを目指しながら医師国家試験に合格した、くふうハヤテ・竹内奎人投手(今季限りで引退)は1つのことに集中し、やり切ってから次へ移るというメリハリを実践。効率を上げるために「何時まで勉強」と時間を区切る習慣や、集中できる環境作りを大切にしていました。こうした事例から、文武両道は精神論ではなく、具体的な"技術"であると解説しています。
・【参加無料】全国制覇チーム監督陣の指導法が学べる5日間!日本一の指導者サミット2025に今すぐ申込む
・守備が苦手な子に共通する体重移動のミスを直す「反復シャドー」
(参考:First-Pitch - ディフェンス)
"小学生の甲子園"「高円宮賜杯 第45回全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」に初出場した明石ボーイズジュニア(兵庫)の総監督を務める筧裕次郎氏(元近鉄、オリックス)が、守備に不安がある選手に多い、間違った捕球姿勢を解消する「シャドーキャッチ」を紹介しました。これは、3つのボールを約1メートル間隔で地面に置き、実際に捕球せず、ステップを踏みながら捕球体勢を繰り返し行うドリルです。3回繰り返す理由として、捕球時に「早く放りたい」や「ボールが怖い」という意識から、頭が投げる方向の左にいき、体重が左にずれてしまうのを意識づけで防ぎたいと説明します。右投げの場合、体重が軸足である右側にあればイレギュラーに対応できる範囲が広がり、送球時の体重移動も安定すると指摘。この地道な基本動作の反復こそが、試合で活躍するための土台になると説いています。
・盗塁成功の鍵は「減速」の技術?単純なランメニューが走塁能力を高めるワケ
(参考:First-Pitch - ランニング)
西武で4年連続盗塁王に輝いた片岡易之(当時、現・保幸)さんをサポートしたプロトレーナー・安福一貴さんが、走力アップと怪我のリスク軽減に繋がる「アクセレーション&ディセラレイトスプリント」を紹介しています。これは、コーン間をダッシュ、減速、再加速と交互に行うシンプルなメニューです。この練習で最も重要視されているのが「全てを緩やかに繋げて行う」こと。メリハリではなく、加速と減速を「緩やかに繋ぐ」感覚を身につけることが目的です。安福氏は、野球の盗塁だけでなく様々な場面で求められる減速や再加速の動きを習得することで、試合中の対応力につながると解説しています。また、誤った減速の仕方は足に負担がかかり怪我のリスクが高まるため、このトレーニングは正確で効率の良い足の使い方を学ぶ場にもなり、具体的な技術を学ぶための土台を築きます。
編集部のコメント
小さな技術や習慣の積み重ねが、選手を大きく成長させます。目の前の練習や勉強に集中する「メリハリ」を意識して取り入れましょう。
関連動画
・【参加無料】全国制覇チーム監督陣の指導法が学べる5日間!日本一の指導者サミット2025に今すぐ申込む
・オリックス・森友哉も実践 ケガ予防、投打が飛躍的に伸びる「身体機能向上プログラム」/久米健夫
・MAX155キロの指導者監修 年代別|好投手育成プログラム/NEOLAB