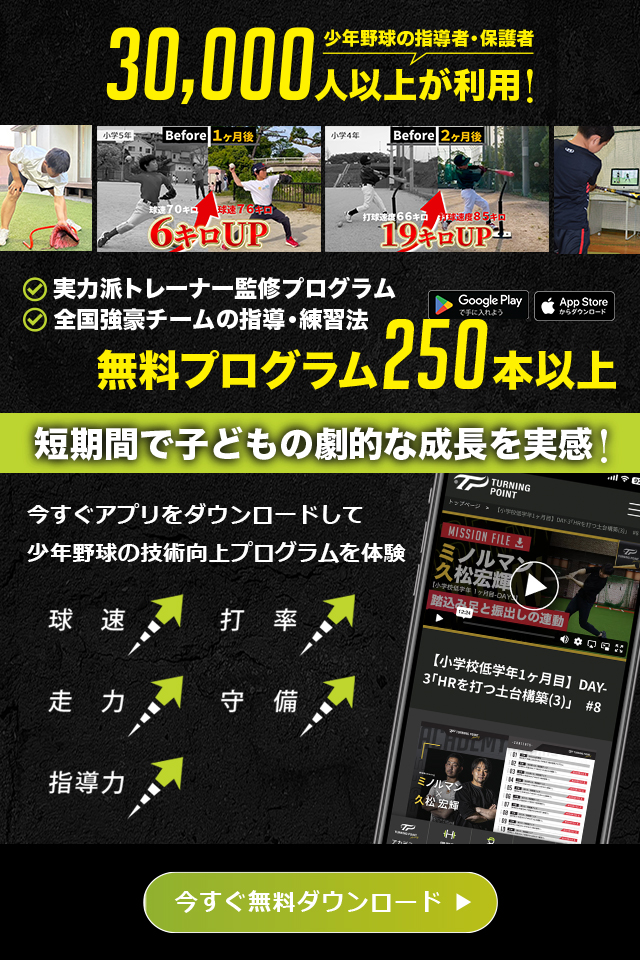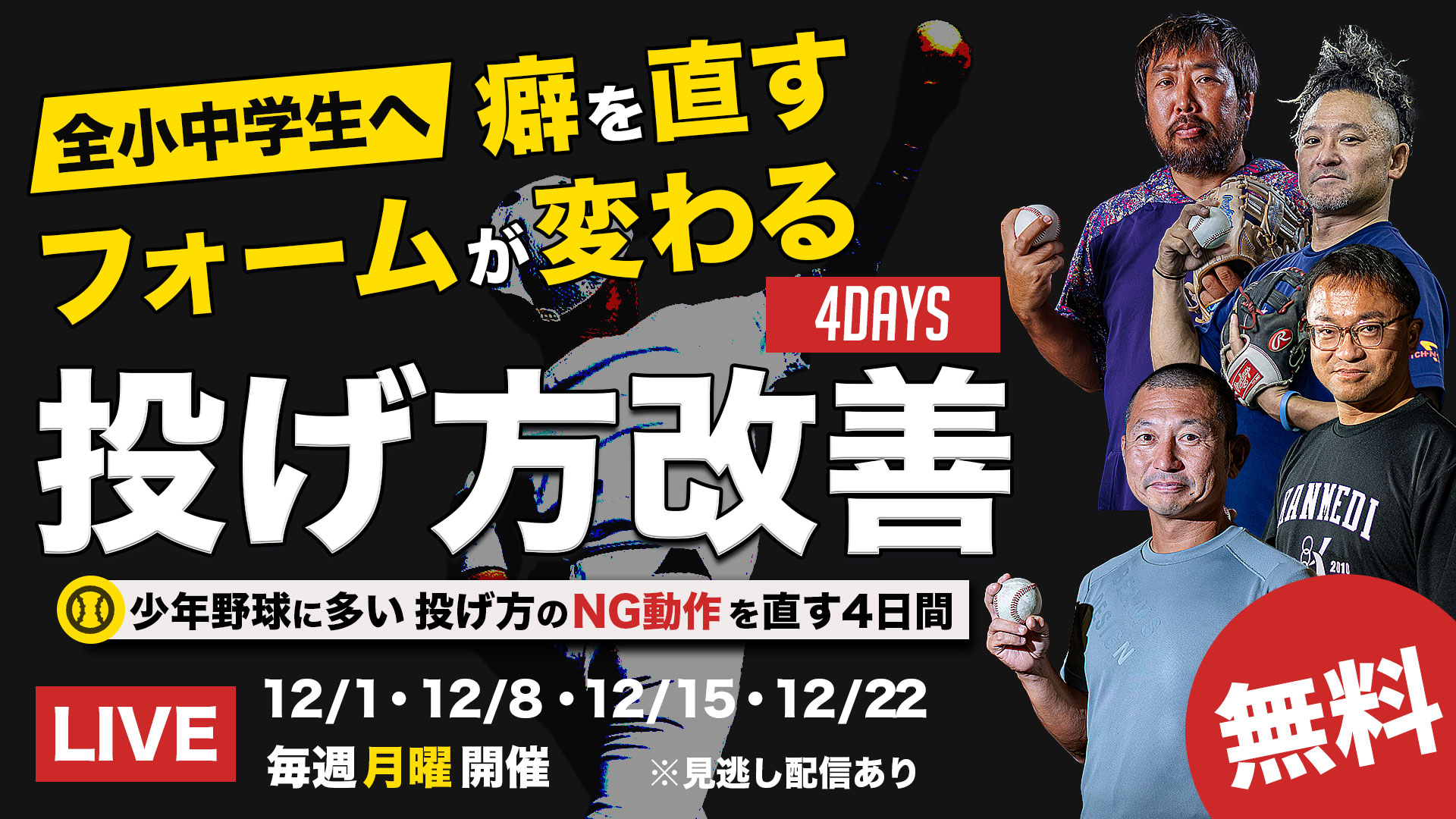子どもが苦しむ“期待”の罠 親の応援が生む健全成長の秘訣
親子で築く信頼 年中夢球氏が提言する応援法
「応援」と「期待」は似て非なるもの。親がその違いを理解しないと、野球を楽しむ子どもたちを無意識に苦しめる可能性がある。保護者と選手のベースボールメンタルコーチとして活動する年中夢球氏が、そのポイントを解説している。応援とは、子どもの努力や楽しみを見守り支えるもので、結果を求める期待とは本質的に異なると話す。
動画内で年中夢球氏が明かしたのは、親の言葉ひとつで子どもに大きなプレッシャーを与えるリスクだ。例えば試合後に「今日ホームラン打った?」と結果を問い詰めるような言葉が子どもにとって重荷になる。また「期待してるからね」といった言葉は、実は親自身のための願望であり、子どもにその重圧を転嫁してしまう。親には「結果ではなく経過」を大切にする姿勢が求められるという。
「期待している親は結果に固執し、応援をする親は経過を見ている」と、年中夢球氏が指摘したように、子どもが自らの課題と向き合うためには親の柔軟なサポートが不可欠だ。特に「今日頑張ってきた?」や「楽しめた?」という親の関与が、結果を重視しすぎない健全な環境を作る。その一方で、結果を重く見た場合、子どもが親の期待に添えずに自己否定感を抱えたり、言い訳に頼ったりするケースも少なくない。
また年中夢球氏は、応援には「ヘルプ」「アシスト」「サポート」という3段階があると説明した。ヘルプ型では親がすべてをやってしまい、子どもの自主性を奪う。アシスト型は、必要な場面での補助や背中を押す行動が含まれる。そして最良の形態はサポートであり、道具の準備やお弁当作りといった間接的支援が中心になる。動画を通じて、親がサポーターとして良い距離感を築くことが子どもたちの健全な成長につながると強調した。
子どもが野球に打ち込む過程では、親もまた共に成長する必要がある。期待の押し付けではなく、頑張ったという事実自体を褒める姿勢。それが、親子の信頼関係を強めるカギとなる。年中夢球氏の言葉は、親としての在り方を見つめ直す機会を私たちに与えてくれる。
関連動画
・オリックス・森友哉も実践 ケガ予防、投打が飛躍的に伸びる「身体機能向上プログラム」/久米健夫
・MAX155キロの指導者監修 年代別|好投手育成プログラム/NEOLAB